

今年度は2部構成です。第1部は6月に日帰りで、第2部は8月に2泊3日で実施。実習助手の小地沢麻樹がコメントいたします。[ ] は指導教員。
| 朝食後の午前8時25分、八幡平ユースホステル前にて、集合写真を撮りました。 カメラマン2名が同時に撮影したので、どちらに目線を送るべきか悩ませてしまったかもしれません。(すみません。) |  |
| お世話になったペアレントにお礼を述べ、八幡平ユースホステルを後にしました。 バスで移動し、茶臼口にて降車。茶臼岳、黒谷地湿原、源太森を経て、八幡沼を目指します。 |  地形 |
| 手には地図とコンパスとデジタルカメラ。地形と植生の関係を探るため、要所要所の特徴を記録しながら歩きました。 |  |
| 午後12時30分頃、八幡沼陵雲荘に到着。 昼食後、国立公園の管理と湿原の植生について、渋谷教授が解説。一般の方も立ち止まり、傾聴なさっていました。 その後、下山しバスで大学へ。 |  国立公園管理 |
| 午後15時50分、大学到着。 実習室に移り、地形調査結果をまとめ、分析しました。与えられた時間は35分。疲労感に襲われながらも、力を振り絞って頑張りました。 |  地形のまとめ |
| まとめた結果と分析を班ごとに発表。それを受け、吉木准教授が詳しく解説しました。 以上で全行程終了。最後に、講座代表の平塚教授より。「こんなに楽しそうに実習する学生は初めてです。お疲れ様でした。」 | 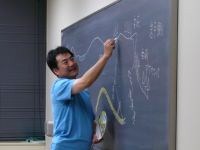 地形の解説 |
 トラップ回収 | 午前6時30分、起床。 朝食前に、昨日仕掛けたトラップを回収。アカネズミ(左)5頭とヒミズ(右)1頭が掛かっていました。1頭ずつ生体重を計測し、元の場所へ放しました。 |
 植生調査 | 朝食後、バスに乗り込みました。今日は午前も午後も植生調査です。 午前中のフィールドは、東八幡平病院北側のコナラ林と、松川地熱発電所西側のブナ林。10m×10mの方形区を設定し、出現種と被度を記録しました。 |
 地熱発電所見学 | 昼食後、松川地熱発電所へ向かいました。展示室見学後、日本の地熱発電について、渋谷教授が解説。 金子教授が、売店でイナゴの佃煮を購入していました。 |
 植生調査 | 午後、台風の影響で、雨が降り始めました。 再び植生調査に戻ります。次のフィールドは蓬莱境。コメツガとオオシラビソ(共にマツ科)の見分け方を習得しました。 |
 水質調査結果のまとめ | 植生調査を早めに切り上げ、八幡平ユースホステルへ。昨日の水質調査結果をまとめ、簡単に考察。 途中、落雷と停電というハプニングもありましたが、動じることなく作業を続けました。 |
 | まとめた結果を班ごとに発表。お互いに情報を共有しました。このデータを基に、後日レポートを作成します。 |
 野鳥調査結果の解説 | 引き続き、第1部で行った野鳥のラインセンサスについて、金子教授が解説。学生の考察を採り上げながら、一層深い捉え方を示しました。 |
 昆虫採集結果の発表 | 夕食後、昆虫採集結果の発表に合わせ、昆虫、ネズミ、野鳥、それぞれの成績優秀者の表彰を行いました。今年度は全7タイトル。受賞者の皆さん、おめでとうございます。 そのまま親睦会開始。金子教授より、イナゴの佃煮が差し入れられました。 |
| 午前8時15分、大学集合。必要な備品を確認し、バスで八幡平市へ向かいました。 最初のフィールドは、松尾鉱山跡の植栽地です。閉山後の植生回復状況や植樹活動について、平塚教授が解説。 |  植生回復 |
| 次は、松尾鉱山跡の中和処理施設。職員さんの案内のもと、施設の屋内外を見学しました。多くの工程がありましたが、最も印象深かったのは、副産物の貯泥池でしょうか。 貯泥池の写真は、過年度の記事に掲載されています。 |  公害 |
| 後藤川温水路で昼食。憩いのひと時を過ごしました。 なお、この水路は、かんがい用水を温めるための施設です。太陽熱や空気に触れる面積を増やし、水温を上昇させています。 |  |
| 午後一番の実習は、河川の水質調査。赤川チーム、松川チームに分かれ、それぞれ3地点ずつ調査を行いました。調査項目は流量、pH、電気伝導度、濁度、透視度、COD、硝酸態窒素など。環境調査実習Iでの練習成果を、存分に発揮できたようです。 |  水質調査 |
| 宿泊先の八幡平ユースホステルへ移動。 さて、到着早々に次の実習です。ネズミを捕えるため、シャーマントラップ(生け捕り用の箱罠)を近くの森林に38個仕掛けました。翌朝回収します。 |  トラップ設置 |
| 夕食後もやはり実習です。屋外で昆虫を採集し、屋内で分類します。ノルマはひとり5種。 懐中電灯と網を振り回しながら、全員が5種ずつ採集しました。 |  昆虫採集 |
| 昆虫の採集を終えると、次は分類作業。図鑑を片手に、採集した昆虫の目名、科名、種名を突き止めていきました。鱗翅目(りんしもく:ガとチョウ)の同定が、特に難解だったようです。 まずは初日終了です。 |  昆虫分類 |
 熔岩流 | 午前8時30分、大学集合。バスで八幡平市へ向かいました。 最初のフィールドは、岩手山焼走り熔岩流です。展望台に登り、吉木准教授が熔岩流の形成過程について解説。 |
 植生遷移 | 上から眺めるだけでなく、実際に熔岩流へ踏み込んで行きます。途中、島田講師が熔岩流に生育する植物の遷移について解説。この場所は、植物の定着に必要な条件がなかなか揃わず、遷移の速度が遅いとのこと。 |
 野鳥のラインセンサス | 次のフィールドは、八幡平樹海ラインです。金子教授の指揮のもと、野鳥のラインセンサスを行いました。出現種はキビタキ、メボソムシクイ、ヒガラ、ウグイスなど。由井名誉教授と渋谷教授の協力もあり、調査は順調に進んだ模様です。 |
 松尾鉱山跡 | 午後一番に、菅原一兄氏(5月28日の環境調査実習Iで来学)が登場。松尾鉱山跡の中和処理施設の敷地から、周辺の様子を観察しました。続いて、「いわて学」から駆け付けた豊島教授と合流し、松尾歴史民俗資料館を見学しました。 |
 マチの死と再生 | 本日最後のフィールドは柏台です。ここはかつて、松尾鉱山に勤めたたくさんの方々とそのご家族が暮らしたマチ。菅原氏の案内のもと、閉山後に整理された区画を歩き回りました。 終着点は、松尾八幡平ビジターセンター。 |
 | センターの一室で、柏台というマチについて考察。松尾鉱山閉山前後で変わったところ、変わっていないところを、学生全員が発表し、倉原教授がKJ法でまとめました。 その後、バスで大学へ。午後6時帰還。 |